7月5日、茨城県の鉾田市を訪問しました。
お会いしてくださったのは、長芋専業農家の箕輪竜さん、竜さんのご両親、普及員の橋本さんです。
竜さんは、大学で学んだことを生かしながら、農業にとても熱心に取り組んでいる若き農業者です。
いくつも倉庫がある箕輪さんのお宅、そのうちのひとつでは、長芋を真空パックにする作業をしている最中でした。
最近は、長芋を一本まるまる買う消費者が少なくなっているため、20cmくらいの長さに切って、
真空パックにして、出荷しています。
普通、長芋の生産期は、秋と春ですが、
箕輪さんは、1年中出荷するため、このような保存方法をとっているそうです。
メロンが生産量NO1の茨城県。この地域は特にメロンを栽培している方が多いそうです。
とてもおいしくて甘いメロンをご馳走してくださいました。
箕輪さんは現在も市場にむかごを出荷し、そのおいしさをもっと伝えたいと考えています。
生協に長芋を出荷なさっている関係で、以前、東京で消費者交流会の際に、むかごご飯を提供したそうです。
大人気ですぐになくなってしまい、むかごの人気ぶりに驚いたとおっしゃっていました。
むかごを懐かしむ年輩の方から、おやつ代わりに、と子どもまで、幅広い世代に受け入れられるのも、むかごの魅力です。
しかし、<どうしてむかごの流通が進まないのか>という現実。
その理由を二つ、お話してくださいました。
①手間の問題
手間がかかるというのは、むかごを収穫するときのことです。
 長芋は地下に成長し、地上にはツルを伸ばし、多くの場合はツルが巻きついていきます。
長芋は地下に成長し、地上にはツルを伸ばし、多くの場合はツルが巻きついていきます。
メインの親ツルがあって、子ツル孫ツルがあって、そこに枝垂れのようにプチプチできるのが、むかごなのです。そして熟したむかごは、ぽろぽろと、土に落ちます。
箕輪さんの畑では、落ちたむかごを一粒一粒手で拾って収穫します。
まだツルについている時にゆすって振り落とす方法や、下に敷いたマルチに落ちたむかごを掃いて集める生産者もおられます。その土地と生産者によって収穫方法は様々です。
それから、虫。
むかごは、土地にもよりますが、虫食いが多い場合があるようです。
水に浮かべて選別したりする方法をとっているようですが、最後は一粒ずつチェックをします。
これが100粒200粒ではなく、百キロなどの世界になれば、気が遠くなるような作業です。
生産者にとって、あくまでメインは地下のイモ。むかごにこんなに手間をかける必要は正直ありません。
そのうえ、この手間や労力が、市場の価格に反映されなければ、扱うだけ無駄になってしまいます。
むかごの可能性をどれだけ見出していくことができるのか、まっとうな価格で流通させることができるのか、とても重要なポイントになるでしょう。
そしてこれらのことは、生産者や流通だけの問題ではなくて、消費者にかかっているともいうことができるでしょう。
つづく・・・

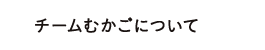

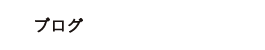
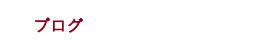
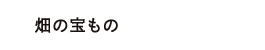

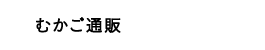





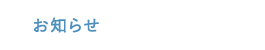
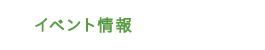
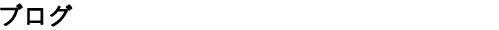

 最近の記事
最近の記事
 カテゴリー
カテゴリー
 アーカイブ
アーカイブ